
パン作りは「生地を捏ねて」「成形して」「発酵させる」
ここまでは良い道具を使わなくても上手にできる「技術」を高められます
てもパンを「焼く」技術はこの上達とはあまり関係ない
なぜなら、
「パンの焼き」だけは道具の性能が非常に大切だからです
それなのに『焼き』次第で美味しいパンと美味しくないパンに分かれてしまいます
そんなもったいないことをしないために
高いオーブンを買わずにできる
「ダッチオーブン」を使って焼く最強なパンの焼き方を紹介します
目次

こんな感じの「鋳造鉄製の鍋」のことをダッチオーブンといいます
今回は焼き方の解説なのでメリット・デメリットだけざっと紹介
- オーブンに直接入れられる設計
- 高い熱伝導率
- 安定した保温性
- 蓋が重いから蒸気を逃がしにくい
- 置き場所に困る
- 思ったより重い
パンを焼くことにおいて非常に重要な
・安定した保温
・蒸気を閉じ込める
この二つの要素を高いレベルで実現してくれるのがダッチオーブンになっています
私のオススメは下の二つ
共通しているのはサイズが24cmと取手も金属でできてる所
| サイズ | 24cm |
| 重量 | 約5㎏ |
| 内容量 | 3.8L |
| サイズ | 24cm |
| 重量 | 約4.4㎏ |
| 内容量 | 1.6L |
こっちはパン専用って感じなので料理などにも鍋として使いたいとお考えの方は上のStaubが断然便利です
Staubと同様の鍋タイプもル・クルーゼは出していますが、取手が樹脂だったりステンレスだったりと写真とは違うものが届くと口コミがあったので注意が必要かなと思いオススメからは外しました
(樹脂だとオーブンの熱に耐えられないから)
もうル・クルーゼのダッチオーブンを持ってるけど取手が樹脂製という方は公式が販売しているステンレス製の取手があるのでそちらの購入を検討してみてください

必要なのは2つ
・ダッチオーブン
・オーブン
オーブンの種類は特に指定なし
家庭用のオーブンでも問題ないし、コンベクション・ガス・電気などで大丈夫です
※パンの種類や重量によって焼き時間や温度が違うのでこのページの下にまとめておきます
※この焼き方は私が言う「絶対に守る5分ルール」などの理想的な焼成条件を満たすやり方です
オーブンの中に蓋ごと入れる
ダッチオーブンを使った焼成(パンを焼くこと)のイメージは
家庭用オーブンの中に一回り小さな超高性能なオーブンを作るような感じです
なのでダッチオーブンを予熱する時は蓋までしっかりと入れてあげます
十分に予熱する
どの種類のパンを焼くかによって予熱の温度は変わりますが、目安は普段焼いている温度+20℃くらいで予熱しましょう
ここで十分に予熱しないとダッチオーブンの効果は半減します
オーブンの電源をつける時に一緒に入れるくらいでちょうどいいと思います
発酵させた生地を入れる
火傷に注意してダッチオーブンを取り出してから蓋を開け、発酵させた生地を直接orベーキングシートごと入れます
Staubのダッチオーブンだと底が深いのでベーキングシートごと入れる方が安全で、ル・クルーゼの方は底が浅いのでどちらでも大丈夫です(私は昔、直接入れようとして火傷したことがあります)
10~15ccの水or氷を入れ、蓋をしてオーブンへ
これはパンを焼く時に入れる蒸気になります
水や氷を入れたらできるだけ早く蓋はしましょう!どんどん蒸発してしまいます
水と比べると氷の方がすぐには蒸発しないのでダッチオーブンの中により多くの蒸気を入れることができます
オーブンへ入れたらオーブンの温度を変更してください(ページ下の表参照)
蓋をした状態で焼き時間の約半分焼く
最低でも5分は蓋をして焼きます
焼成中の最初の5分は蓋を外して中を確認するなんてことはしないでください
今回紹介しているダッチオーブンを使う焼き方の中でもポイントです!
最初の方に言った理想的な焼成条件についてや絶対に守る5分ルールなどはRiopan’sメンバーの焼成についての基礎理論で詳しく解説しているのでRメンバーに興味がある方はリオの公式LINEからご確認ください
半分経ったら蓋を外して焼き色が付くまで焼く(残り半分)
ダッチオーブンで焼いていると蒸気が十分にあるので蒸し焼きや白米を炊いている状態に近い為、蓋をしたままだとパン表面の焼き色が付きにくいです
なので蓋を外して蒸気を逃がし、焼き色を最後につけてあげます
焼き時間の半分はあくまでも目安になり、芯温と色付きのバランスを見て決めるのがベストです
| パン生地の種類 | 温度 | 時間 |
|---|---|---|
| リーンな生地 | 250℃⇒230℃ | 20分(小さいと13分) |
| リッチな生地 | 220℃⇒200℃ | 11分(大きいと25分) |
この表はあくまでも目安です
温度は大きく変更しなくてもなんとかなりますが、時間は結構前後します
レシピ毎に糖の量が違ったり、発酵によって糖を分解されたりもするので一概に何分とは言い難いです
例)カンパーニュやバケット、ロデブ、クッペなど
これらはできるだけ高温でサクッと焼くのが美味しいです
例)あんぱんやメロンパン、編み込みパンなど
こちらもできるだけ高温でサクッと焼くのが美味しいですが、
生焼けになりやすかったり焦げやすいのでリーンなパンよりも低い温度で焼きます
生焼けかどうかは竹串を刺して判断するのも良いですが
オススメは温度計を刺してみて94~96℃を超えているかどうかを確認してみてください!
- 焼き色だけでは焼けたか判断できない
- 砂糖の量とミルク類(粉乳含む)で焼き色が変わる
- 生地や発酵状態がベース
- オーブンの予熱完了通知はその温度に達していないこともある
パンに限らず、お肉や魚でも見た目だけで焼けたかどうかは分かりません
焼けたかどうかを判断するには竹串をさして生地がついていないかどうか確認する方法が一般的ですが、
オススメは温度計をさしてみて94~96℃を超えているかどうかを確認する方法です
芯温が何℃になっているかは焼けたかどうかの判断にもなるし、ちゃんと殺菌できたかどうかの目安にもなります
ちなみに私は芯温が96℃を超えていなければ生焼けと判断しています(見た目や内層が良さそうでも消化に悪いから)
砂糖の量とミルク類の有無はパンの焼き色の付きやすさが変わってきます
・砂糖多い→焼き色◎
・砂糖少ない→焼き色付きにくい
・ミルク類有り→焼き色◎
・ミルク類なし→焼き色付きにくい
焼き色の付きやすさ=焦げやすさ=生焼けのなりやすさ
でもあるので、芯温がちゃんと94~96℃になるように焼こうとするとリーンな生地とリッチな生地のような温度と時間になります
先ほどの糖は発酵でも使われてしまうので入れた砂糖の量が多いからといっても焼き色があまりつかないことがあります
なので「焼き」がいかに良くても生地作りや発酵の状態でパンの美味しさは変わってしまいます
『焼き』にすべての原因があるとは限らないので注意しましょう!
意外な落とし穴で、温度が上がりましたよーっていう通知音が鳴った後にオーブンの温度を温度計で測ると5~10℃くらい低いことがほとんどです
オーブンによる違いもありますが、
・通知が鳴ってから少し待ってあげたり
・5~10℃高く設定
した方がしっかりと予熱されることが多いです
ダッチオーブンとは「鋳造鉄製の鍋」のこと
- オーブンに直接入れられる設計
- 高い熱伝導率
- 安定した保温性
- 蓋が重いから蒸気を逃がしにくい
- 置き場所に困る
- 思ったより重い
パンを焼くことにおいて非常に重要な
・安定した保温
・蒸気を閉じ込める
この二つの要素を高いレベルで実現してくれるのがダッチオーブン
私のオススメは以下の二つ
| サイズ | 24cm |
| 重量 | 約5㎏ |
| 内容量 | 3.8L |
| サイズ | 24cm |
| 重量 | 約4.4㎏ |
| 内容量 | 1.6L |
こっちはパン専用って感じなので料理などにも鍋として使いたいとお考えの方は上のStaubが断然便利です
必要なのは2つ
・ダッチオーブン
・オーブン
オーブンの種類は特に指定なし
家庭用のオーブンでも問題ないし、コンベクション・ガス・電気などで大丈夫です
この方法はパン屋さんの安い業務用オーブンよりも良い焼成条件をクリアできます
ではなぜパン屋さんがこの方法をしないのかと言うと
・焼ける空間が減ってしまう
・たくさん焼いているから手間がかかる
この二つの理由が大きいでしょう
なのでこの方法は家庭で焼くのに最強で最適なんです!
・250℃⇒230℃
・蒸気多め
・20分(350g前後)
・13分(60g前後)
・220℃⇒200℃
・蒸気多め
・11分(60g前後)
・25分(350g前後)
- 焼き色だけでは焼けたか判断できない
- 砂糖の量とミルク類(粉乳含む)で焼き色が変わる
- 生地や発酵状態がベース
- オーブンの予熱完了通知はその温度に達していないこともある
今回紹介したダッチオーブンを使った焼き方はパン焼成の理想が詰まっています
それができるのは作る量がパン屋さんほど多くない家庭だけです(もし業務用オーブンで実現しようとすると1000万くらいが最低ライン)
パンの焼き時間や温度は同じレシピを使っていても
その人によって190℃で15分だったり、210℃で11分だったりと違いがあります
私が紹介する方法は基本的に高温でサクッと焼くことで、
パンのふっくら感やジューシー感を最大限に発揮させるようにしています
違う考えの方もいるのであくまでも参考程度にしていただけると幸いです
最後までご覧いただきありがとうございます
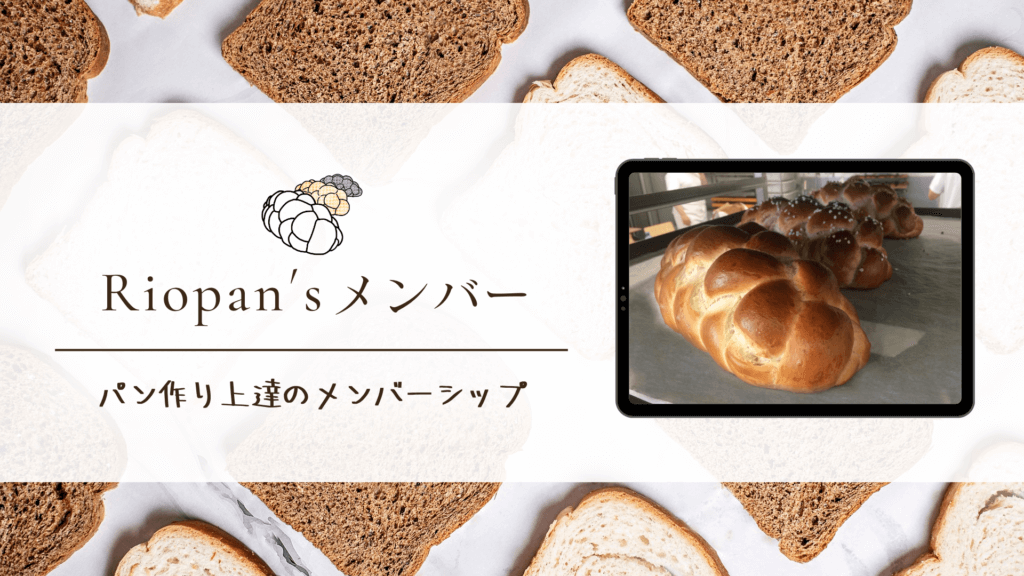
パン作り上達特化の「Riopan’sメンバー」
「あなたの抱えてるパン作りの疑問」「教えてる内容に自信を持てない」「習ってる内容と過去に習った内容の矛盾に困っている」そんな方の後押しをして、
1年後、2年後には「何か失敗があっても自分で原因を見つけ解決法を考えられる」「教えてる内容に自信が持て、生徒の質問に即座に答えられる」
その為にはパン作りの基礎的な理論、理論を紐付ける体系的な知識、実際に作った経験を積んでいく必要があります。
Riopan’sメンバーでは基礎的なパン理論講座、体系的な知識にしていく方法、実践で感じた疑問やどこにも載ってない疑問に回答するチャットを無制限でご覧いただけます。

